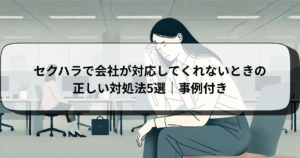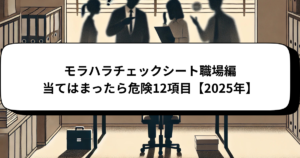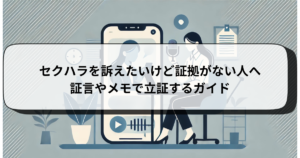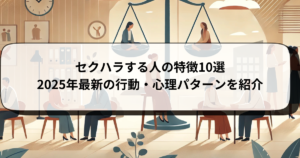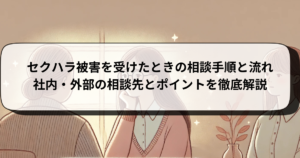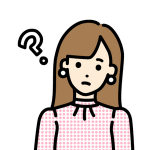
「セクハラ加害者って、その後どうなるんだろう?」
職場でセクハラの被害を受けた経験がある方や、現在関わっている方にとっては、とても気になるテーマではないでしょうか。
「加害者はその後、ちゃんと処分されているのか?」
「自分とまた関わる可能性があるのか?」
そんな不安や疑問を少しでも解消するために、この記事では実際の事例や企業の対応を交えながら、加害者の“その後”について詳しく解説します。
カンタンな自己紹介
はじめまして。40代の自営業者です。
私は過去に、職場で深刻なパワハラ被害を受けた経験があります。
流れ
- 上司からパワハラを受ける
- 社内のコンプライアンス窓口と労基に相談
- メモにまとめて、証拠として提出
- 加害者は「降格」と「減給」の処分を受ける
この体験をきっかけに、ハラスメント対策や労働法について学び、現在はハラスメントに悩む方に向けて、実体験をもとにした情報を発信しています。
1. セクハラ加害者はその後どうなる?懲戒・転職・私生活への影響まとめ


1-1. 懲戒処分の内容とは?懲戒解雇・減給・降格の実例
「セクハラをした人って、その後どうなるの?」――そんな疑問をお持ちではありませんか?
実際、セクハラ行為が明るみに出ると、加害者はさまざまな懲戒処分を受けることがあります。
例えば、ある企業では、
部下に対する不適切な言動が原因で、管理職から一般職への降格処分が下されたケース
があります。
また、別の企業では、セクハラ行為が重大と判断され、懲戒解雇に至った事例も報告されています。
これらの処分は、企業の就業規則や行為の内容、被害の程度などによって異なりますが、共通しているのは、
加害者が社会的な信用を大きく失う
という点です。



「加害者がどんな処分を受けるのか気になる…」というお気持ち、よくわかります。
実際の事例を見ると、セクハラ行為が決して軽視されていないことがわかりますね。
1-2. 転職先は見つかるのか?再就職の実態と企業の対応
セクハラ行為が原因で退職した場合、再就職はどうなるのでしょうか?
実際、前職でのセクハラ行為が公になってしまうと、転職活動はすこし厳しくなります。
特に同じ業界内では情報が共有されやすく、採用担当者が慎重になる傾向があります。
そのため、加害者は異なる業界への転職を試みたり、フリーランスとして新たな道を模索するケースもあります。



加害者は前職と同じ業界をえらぶ可能性がほとんど。
僕の会社でパワハラしていた人もそうでした・・・ 業界同士ってかなり情報が共有されやすいんですよね。
また、
企業側も採用時に過去のハラスメント歴を確認する動きが強まっており、再発防止のための研修受講歴などを求める
ことも増えています。



「加害者が転職してしまったら、もう関係ないの?」と感じるかもしれませんが、実際には再就職先でも過去の行為が影響を及ぼすことが多いようです。
1-3. 家族・友人関係への影響は?孤立や信頼の失墜事例
セクハラ行為は、職場だけでなく、加害者の私生活にも深刻な影響を及ぼします。
例えば、
ある男性は職場でのセクハラが原因で家族に知られ、夫婦関係が悪化し、最終的には離婚に至ったケース
があります。
また、友人や知人からの信頼を失い、社会的に孤立してしまうことも少なくありません。
これらの事例から、セクハラ行為が個人の生活全般に及ぼす影響の大きさが伺えます。



「加害者の私生活への影響ってどうなんだろう?」と気になる方も多いでしょう。
実際の事例を見ると、職場以外でも大きな代償を払っていることがわかりますね。
2. 被害者にとって「加害者のその後」はどう関わってくるのか


2-1. 加害者が社内に残った場合の心理的負担と対応策
加害者が同じ職場に留まる場合、被害者は日々の業務で顔を合わせることになり、大きな心理的負担を感じることがあります。



実際には、加害者と被害者が遭遇しないように工夫してくれるパターンがほとんど。
僕の会社では、加害者が1人だけの部署に隔離されていました。
安心できない環境では、まず信頼できる上司や人事部門に相談し、配置転換や業務内容の見直しを検討してもらうことが重要です。
また、社内に相談窓口が設置されている場合は、そちらを利用するのも一つの方法です。
被害者が安心して働ける環境を整えることは、企業の責任でもあります。



「加害者がまだ職場にいるなんて、どうしたらいいの?」と悩むお気持ち、よくわかります。
まずは信頼できる人に相談することから始めてみませんか?
労働局や法律相談所でも相談できます。
2-2. 異動・転職などで物理的距離はとれるのか?
加害者が異動や転職をすることで、被害者との物理的な距離が生まれる場合もあります。
しかし、異動や転職が必ずしも迅速に行われるわけではなく、その間の対処が必要です。
被害者自身が異動を希望する場合もありますが、これは被害者にとって二次的な負担となる可能性があるため、慎重な判断が求められます。
企業としては、
被害者が安心して働ける環境を提供するために、迅速かつ適切な対応を行う責任
があります。



「物理的に離れることができれば…」と考えるのは自然なことです。でも、そのためにあなたが無理をする必要はありません。
2-3. 謝罪や接触はある?実際の加害者の行動パターン
セクハラの加害者がその後どう行動するかは、人によって大きく異なります。
- 「謝罪に来るのか?」
- 「何か言ってくるのか?」
と不安に思われる方も多いでしょう。
実際には、企業や法的なアドバイスを受けた結果、加害者側が「接触を避ける」方針を取ることも多いです。
たとえば、被害者の感情をさらに傷つけないようにするため、直接の謝罪ではなく、第三者を通じて謝意を示すケースもあります。
一方で、まれに謝罪を求められることもありますが、その場合は慎重な対応が必要です。
感情的なやり取りを避けるためにも、専門の相談窓口や弁護士などを介してやり取りを行うことが推奨されます。



「謝罪されるのか分からない不安」って、すごく消耗しますよね。
でも、無理に受け入れる必要はありません。あなたの心が最優先です。
3. 加害者の再教育や再発防止の実態とは?


3-1. 企業が実施する再発防止研修・カウンセリングの内容
セクハラ加害者に対し、再発防止を目的とした研修やカウンセリングを行う企業も増えてきました。
例えば、
- コンプライアンス教育に特化した外部機関による講義
- 心理カウンセリングの受講義務
などが代表的です。
ある企業では、加害者が半年間にわたりカウンセリングを受けたうえで、定期的に報告書を提出する仕組みを導入しています。
これは、再発防止を明確にするだけでなく、企業の責任も果たす重要なステップです。



「加害者が何も反省していないのでは?」という不安、よくわかります。
ですが、企業によっては具体的な再教育を進めているところもあるんです。
最後に
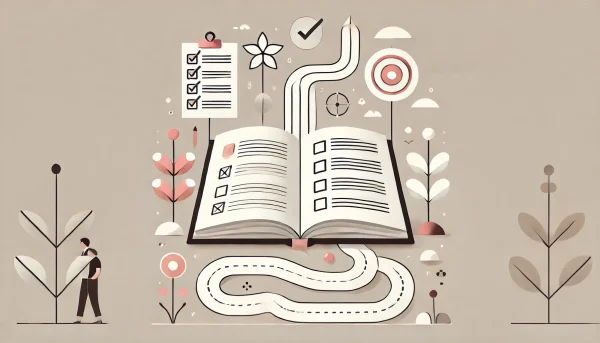
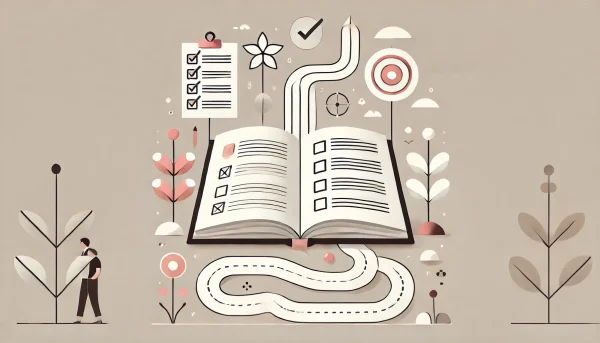
セクハラ加害者のその後としては、かなり厳しい状況となります。
まず会社の全スタッフにセクハラされたことが共有されますし、もし法律的に裁かれた場合、刑罰も残ります。
つまり、次に罰せられたときに罪が重たくなります。
さらには、加害者は同じ業界で働くケースがほとんどのため、業界で何をしたのかを共有される可能性が高いです。
セクハラをしたなんて事がバレたら、新しい会社に居れることなんてもうできないですよね・・・
自分はハラスメントで降格・減給処分された人間なんだ
とい負い目を一生背負っていくことになるので、末路としては最悪なことになるでしょう。



僕は前の会社でパワハラをした加害者が処分され自己退職へ。
その後ばったり偶然、加害者の職場でお会いしたことがありましたが、かなり挙動不審でしたね
もしあたらしい会社に「パワハラで処分された」なんてことがバレたらいてもたってもいられないし、僕の発言ひとつで仕事がまともにできない環境になるのも怖かったのでしょう
そう考えるとハラスメントという行為は絶対にしてはいけないことがわかりますね